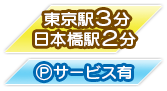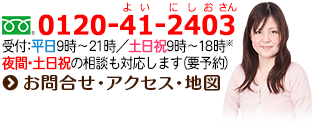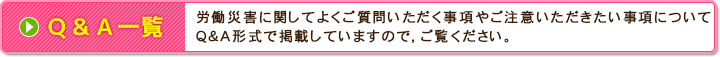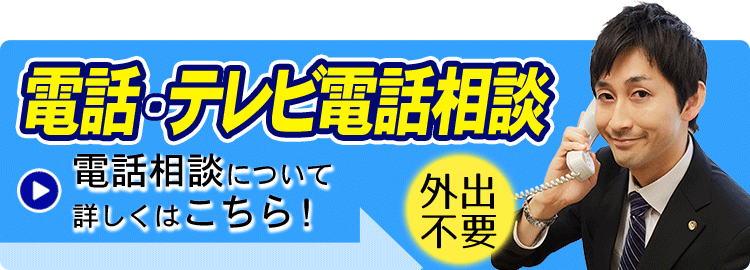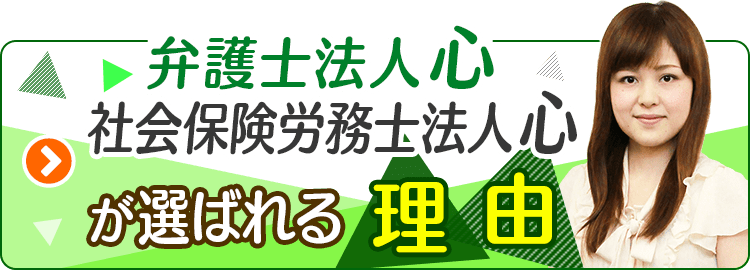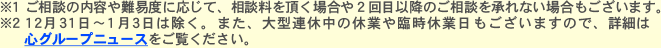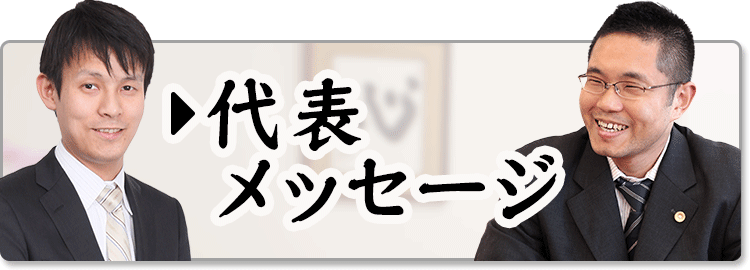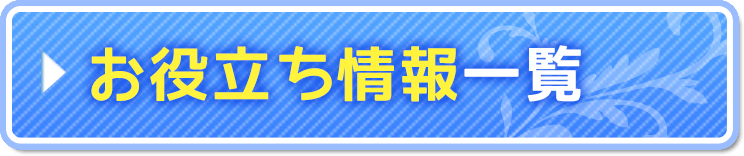大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
お役立ち情報
労災の休業補償について
1 休業(補償)給付とは
労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業(補償)給付が支給されます。
この記事では、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署作成の「労災保険 休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」を参考に詳細を説明しております。
2 給付の内容
⑴ 3要件
下記3要件を満たす場合に、4日目から、休業(補償)等給付と休業特別支給金が支給されることになります。
①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため
②労働することができないため
③賃金を受けていない
⑵ 支給額
支給額の計算方法は、下記のとおりです。
ここでは、便宜上、勤務先が1か所である単一事業労働者の場合を紹介します。
休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数
⑶ 休業の1日目から3日目までについて
この期間を待機期間といます。
この期間は、業務災害の場合、事業主が労働基準法76条の規定に基づいて、休業補償を行うことになります。
しかし、通勤災害の場合や複数業務要因災害の場合には、事業主が休業補償を行わなければならない法令上の規定はありません。
3 給付基礎日額
⑴ 給付基礎日額とは
原則として、労働基準法の平均賃金に相当する金額が給付基礎日額とされています。
平均賃金とは、原則として、
①業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日
または
②医師の診断によって疾病の発生が確定した日
の直前3か月間に被災労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われた賃金は除きます)を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額とされています。
4 一部負担金
通勤災害により療養給付を受ける場合、初回の休業給付から一部負担金として200円(日雇特例被保険者については100円)が減額されてしまいます。
5 時効
休業(補償)等給付は、休業して賃金を受けていない日ごとに請求権が発生しているのですが、2年を経過すると時効により請求権が消滅します。
ある程度まとめて請求をかけようとする場合には、2年間という期間に気をつけて、時効で消滅してしまわないように注意が必要です。
アルバイトが労災に遭った場合の対応方法 労災の特別支給金とは